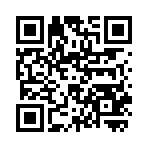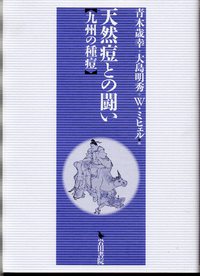浅田宗伯の大奥診療記録(4)、実成院、七宝の間
2015年09月20日
浅田宗伯の診療記録には、天璋院のほかに本寿院ともうひとり実成院が出てくる。実成院(1821~1904)は、御三家の紀州徳川家の藩主徳川斉順の側室で、14代将軍となった徳川家茂の生母である。名前は美佐(みさ)、操子。美喜、於美喜の方ともいう。江戸赤坂の紀州藩邸で菊千代(のちの慶福・家茂)を生んだ。家茂が将軍になったことで、江戸城大奥にはいったのだが、すでに、新将軍生母の住まいである新御殿には家定生母本寿院が住み、御台所御殿には先代将軍家定御台所の天璋院が居住していたため、実成院は七宝の間に居住した。慶応4(1868)年の江戸城開城にともない、静寛院宮(和宮)とともに清水邸(田安徳川家説もあり)の屋敷に移っていた。しかし、和宮が明治2年に京都へ移ったため、天璋院らと一緒に住むことになったとみられる。明治10年に千駄ケ谷に徳川邸ができるとそこに移り、1904年に84歳で死去。寛永寺に本寿院と並んで葬られている。法名は実成院殿清操妙壽大姉という。診療記録には、次のようにある。
一 七宝之間 実成院様
御油薬 中黄 中貝 龍騰飲加紅藍 将中大 九月晦
実成院が七宝の間というのは、先にのべたように、江戸城大奥での実成院の住んでいた間のことである。江戸城開城後も、大奥当時の部屋の名前を使っていた。実成院の処方は、油薬で中黄を使っている。中黄は中黄膏のことで、華岡青洲が編み出した皮膚病やかゆみ止めの薬で、切れ痔やいぼ痔にも効くといわれる。中貝とはサジのかわりに中程度の貝を使うこと。龍騰飲とは、産科の賀川家の処方で、大黄5分、黄連・川芎などを各1銭調合したもので、大黄が、消炎・止血 ・緩下作用があり、瀉下剤として便秘薬に配合されるので、もしかすると、ひょっとすると、実成院は、痔ではなかったかと推測される。でも単なる湿疹かぶれのたぐいかもしれないので、あまり期待しないほうがよいかも。将中大はよくわからないが、中将湯を多めに処方したということではないか。中将湯は婦人薬で血の道症、更年期障害、不安神経症などに効くという。ツムラの中将湯がいまでも著名。実成院は明治4年(1871)は50歳、痔で更年期障害で不眠症でもあったらしい。これらも野中源一郎さんが、正確に分析してくれるだろう。9月27日のシンポがますます楽しみである。
一 七宝之間 実成院様
御油薬 中黄 中貝 龍騰飲加紅藍 将中大 九月晦
実成院が七宝の間というのは、先にのべたように、江戸城大奥での実成院の住んでいた間のことである。江戸城開城後も、大奥当時の部屋の名前を使っていた。実成院の処方は、油薬で中黄を使っている。中黄は中黄膏のことで、華岡青洲が編み出した皮膚病やかゆみ止めの薬で、切れ痔やいぼ痔にも効くといわれる。中貝とはサジのかわりに中程度の貝を使うこと。龍騰飲とは、産科の賀川家の処方で、大黄5分、黄連・川芎などを各1銭調合したもので、大黄が、消炎・止血 ・緩下作用があり、瀉下剤として便秘薬に配合されるので、もしかすると、ひょっとすると、実成院は、痔ではなかったかと推測される。でも単なる湿疹かぶれのたぐいかもしれないので、あまり期待しないほうがよいかも。将中大はよくわからないが、中将湯を多めに処方したということではないか。中将湯は婦人薬で血の道症、更年期障害、不安神経症などに効くという。ツムラの中将湯がいまでも著名。実成院は明治4年(1871)は50歳、痔で更年期障害で不眠症でもあったらしい。これらも野中源一郎さんが、正確に分析してくれるだろう。9月27日のシンポがますます楽しみである。