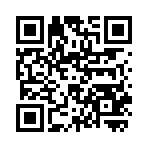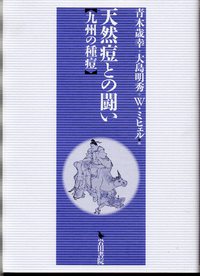適塾48号
2015年12月20日
◆適塾48号が届いた。内容が一新され充実している。いくつか興味ある論考が目に付いた。木村直樹「「華夷変態」から蘭学へ」は、17世紀の明清交替という「華夷変態」と日本近海における紛争激化に触れ、18世紀の安定したアジアの海の鎮静化により蘭学へのまなざしが醸成され、海防のための基礎科学として天文学・軍事科学・基礎科学・医学・地理学などを学ぶために、本格的に蘭学が受容されるようになり、19世紀の本格的な蘭学の、政治性と軍事性を帯びた展開へとつながるとした。外的条件だけでなく、蘭学受容の内発的欲求、知的状況についての分析もほしいと感じたのだが、とても明晰な論考であった。◆村田路人「幕末期大坂地域と洪庵・適塾ー種痘事業を中心に-」は、大坂には個別領主支配と幕府広域支配の二つの支配が展開していたこと、嘉永2年牛痘伝来以後洪庵らの種痘事業が、安政5年(1858)除痘館が官許となるにいたり、種痘事業が個別領主支配下領域において実施されたこと、慶応3年5月の除痘館の公官化により、それまでとは質の異なる広域的な種痘行政が出現したことなどを述べている。また廣川和花氏は、海原亮『江戸時代の医師修業、学問・学統・遊学』の書評を載せている。海原氏は、「学問」「学統」「遊学」によって形成される医師の修学形態の解明から江戸時代の「医療環境」の成り立ちを論じているとした。海原氏の「医療環境」論は、医療を「医者・患者・病気」の複合体である「ヒポクラテスの三角形」の概念でとらえ、それらを含む要素の総合的研究へと変容しつつあるとした。とくに本書では、近世日本の医者の専門的医学教育システムの解明を行ったとしている。評者はヨーロッパにおける18世紀後半からの医療・教育・臨床の場としての「病院」の意義を紹介し、著者の医師の臨床教育が「遊学」先の私塾やその往診先であったことに、近世日本の医療を特徴づける点の一つであったとする。近世日本の医学史研究にヨーロッパとの比較史の視点と、近世・近代の「断絶」との視点、とくに「病院の不在」をあげているのは、書評を超えた論考になっているともいえよう。近世日本医学史研究に寄与することの多い鋭い指摘である。