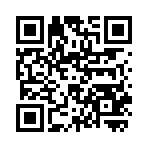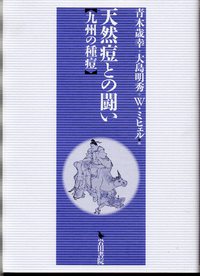新刊紹介『一滴』24号
◆津山洋学資料館の研究誌『一滴』24号が届いた。4月23日(日)に瀬能宏地球博物館学芸部長による「箕作の名をもらった魚たち」の講演会案内も同封されていた。ミツクリザメなど箕作佳吉の調査により、ミツクリの名をもらった魚類は14もあるようです。関心のお持ちの方は津山洋学資料館まで。◆『一滴』の内容は、幸田正孝「『菩多尼訶経』の危うさ」、臺由子「箕作阮甫による蘭語の博物館関連用語の和訳について」、野村正雄「ナポレオン伝と箕作院甫ベルアリアンセ/スコーンフルボンド戦記を中心に」、吉田忠「柴田収蔵の集書活動ー『柴田収蔵日記』に出る蘭学関係書-」のほか、企画展紹介として、「久原洪哉生誕190周年記念 津山藩医久原家の幕末・明治」、「明治天皇の侍医頭 岡玄卿」、「解剖図の世界一江戸から現代へ」、「津山藩の絵師鍬形家と洋学者」、翻刻として土井康弘「『錦窠先生通信録』坤、補にある伊藤圭介の川口嵩宛書簡の翻刻」などを掲載。
◆吉田忠氏による柴田収蔵(伊東玄朴門人)の江戸での収集活動の論考に関心を持った。吉田氏は、詳細に柴田収蔵の集書活動を日記から読み解き、下以の結論を導いた。
◆「以上収蔵の集書活動を見てきた。医師にをる以前の佐渡時代には、当然のことながら医書には見るべきものはない。ただ蘭学の一般書『蘭学階梯』、『蘭学侃鯖』、『紅毛雑話』、『万国新語』を入手していたことは、収蔵が早くから蘭学に関心をもっていたことを示している。郷里で開業した弘化3年から嘉永元年の時期は、両津の藤沢明卿や小木の小野長庵など地元医師との交流を通じ、蘭学関係の医書を貸借し、写し、読み、学習している。嘉永3年の3度目の江戸遊学では、伊東玄朴塾でチットマン外科書の講読、文典の句読を受け、会読に参加してオランダ語の修得につとめた。そのせいか、開業医時代に比べ、書物の謄写の時間が少ない。安政3年の『日記』になると、既に蛮書調所出役が内定しているせいか、医学よりも地理を初めとする分野の書へと関心が移っているように見受けられる。また開国以後という時代を反映し、英語関連の文献、西学漢籍、新聞などが『日記』に登場する。その後の収蔵の活動を記す『日記』はない。しかし現存する6種の『日記』からだけでも彼の集書活動を充分に追跡でき、佐渡における活発な書物のやりとり、玄朴塾における書物をめぐる動向など豊富訓育報が得られる」という。
◆吉田忠氏による柴田収蔵(伊東玄朴門人)の江戸での収集活動の論考に関心を持った。吉田氏は、詳細に柴田収蔵の集書活動を日記から読み解き、下以の結論を導いた。
◆「以上収蔵の集書活動を見てきた。医師にをる以前の佐渡時代には、当然のことながら医書には見るべきものはない。ただ蘭学の一般書『蘭学階梯』、『蘭学侃鯖』、『紅毛雑話』、『万国新語』を入手していたことは、収蔵が早くから蘭学に関心をもっていたことを示している。郷里で開業した弘化3年から嘉永元年の時期は、両津の藤沢明卿や小木の小野長庵など地元医師との交流を通じ、蘭学関係の医書を貸借し、写し、読み、学習している。嘉永3年の3度目の江戸遊学では、伊東玄朴塾でチットマン外科書の講読、文典の句読を受け、会読に参加してオランダ語の修得につとめた。そのせいか、開業医時代に比べ、書物の謄写の時間が少ない。安政3年の『日記』になると、既に蛮書調所出役が内定しているせいか、医学よりも地理を初めとする分野の書へと関心が移っているように見受けられる。また開国以後という時代を反映し、英語関連の文献、西学漢籍、新聞などが『日記』に登場する。その後の収蔵の活動を記す『日記』はない。しかし現存する6種の『日記』からだけでも彼の集書活動を充分に追跡でき、佐渡における活発な書物のやりとり、玄朴塾における書物をめぐる動向など豊富訓育報が得られる」という。