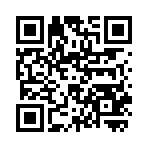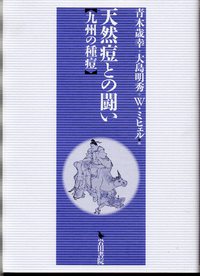新刊紹介 『近世後期の対外政策と軍事・情報』
「郵便です」。午前中の畑仕事を一段落して家に戻ると、ちょうど書籍郵便物が届いた。みると、依頼主は吉川弘文館。封をあけるとなかから、立派な『近世後期の対外政策と軍事・情報』という本で,著者は松本英治さんだった。そうか、とうとう今までの研究を本にしたかと、感慨がよみがえった。
今から15年ほど前、歴博歴史研究部の高橋敏先生の紹介で、私が国立歴史民俗博物館の外部研究「地域蘭学の総合的研究」(平成11~15年度)の代表者を務めたことがある。そのとき、地域蘭学の視点で、福岡の蘭学者青木興勝の研究をお願いしたのが、松本英治さんであった。松本英治さんは、現職の開成・中・高校教諭として教鞭をとるかたわら、洋学史研究会の事務局長として例会の案内をされつつ、洋学研究を続けてきた。
本書の目的は、「寛政期から文化期にかけての西洋諸国の通称要求とそれに起因する対外紛争を、近世日本が直面した対外的危機ととらえ、これが対外交渉の窓口である長崎に及ぼした影響を軍事と情報の視点から論じるとともに、幕府の軍事的・外交的対応を政策的に明らかにすることを目的とする」とある。
本書の目次をひもとけば、第一部、対外的危機と長崎の地域社会、第1章長崎警備とロシア船来航問題、第2章蘭学者青木興勝の長崎遊学と対外認識、第3章レザノフ来航予告情報と長崎奉行、第二部 対外的危機と幕府の軍事的・外交的対応として、第1章フヴォストフ文書をめぐる日蘭交渉、第2章阿蘭陀通詞の出府と訳業、第3章幕府の洋式軍艦導入計画、第4章幕府の戦時国際慣習への関心、第三部幕府の対外政策と長崎の地域社会、第1章大槻玄沢と幕府の対外政策、第2章ラッフルズの出島接収計画と長崎奉行、第3章ゴローニン事件と天文方、終章、対外政策と軍事・情報となっている。
現在、それらについて詳細に読み解く時間と力はないが、関連研究をほぼ網羅し、関連史料を博捜し、その論の進め方は着実であることは疑いをまたない。佐賀藩の警備記録や動向についても教えられることが多い。
現場の高校における研究の困難さは、私の時代よりもはるかに厳しいものがあろう。あとがきを読めば、幸いに同僚の日本史担当教師もまた歴史研究者である。開成中・高校の自由な校風も、松本さんの研究心をささえるものとなったのであろう。かっての若手研究者も、不惑の年をすぎて、43歳となった。さらなる研究のたかみを期待してやまない。
今から15年ほど前、歴博歴史研究部の高橋敏先生の紹介で、私が国立歴史民俗博物館の外部研究「地域蘭学の総合的研究」(平成11~15年度)の代表者を務めたことがある。そのとき、地域蘭学の視点で、福岡の蘭学者青木興勝の研究をお願いしたのが、松本英治さんであった。松本英治さんは、現職の開成・中・高校教諭として教鞭をとるかたわら、洋学史研究会の事務局長として例会の案内をされつつ、洋学研究を続けてきた。
本書の目的は、「寛政期から文化期にかけての西洋諸国の通称要求とそれに起因する対外紛争を、近世日本が直面した対外的危機ととらえ、これが対外交渉の窓口である長崎に及ぼした影響を軍事と情報の視点から論じるとともに、幕府の軍事的・外交的対応を政策的に明らかにすることを目的とする」とある。
本書の目次をひもとけば、第一部、対外的危機と長崎の地域社会、第1章長崎警備とロシア船来航問題、第2章蘭学者青木興勝の長崎遊学と対外認識、第3章レザノフ来航予告情報と長崎奉行、第二部 対外的危機と幕府の軍事的・外交的対応として、第1章フヴォストフ文書をめぐる日蘭交渉、第2章阿蘭陀通詞の出府と訳業、第3章幕府の洋式軍艦導入計画、第4章幕府の戦時国際慣習への関心、第三部幕府の対外政策と長崎の地域社会、第1章大槻玄沢と幕府の対外政策、第2章ラッフルズの出島接収計画と長崎奉行、第3章ゴローニン事件と天文方、終章、対外政策と軍事・情報となっている。
現在、それらについて詳細に読み解く時間と力はないが、関連研究をほぼ網羅し、関連史料を博捜し、その論の進め方は着実であることは疑いをまたない。佐賀藩の警備記録や動向についても教えられることが多い。
現場の高校における研究の困難さは、私の時代よりもはるかに厳しいものがあろう。あとがきを読めば、幸いに同僚の日本史担当教師もまた歴史研究者である。開成中・高校の自由な校風も、松本さんの研究心をささえるものとなったのであろう。かっての若手研究者も、不惑の年をすぎて、43歳となった。さらなる研究のたかみを期待してやまない。